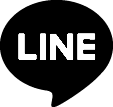ぎっくり腰とは?ぎっくり腰の主な症状と対処法
ぎっくり腰
ぎっくり腰はこんな症状
ぎっくり腰とは、正しくは「急性腰痛症」と言います。
ケガの中でも知名度が高く、患者さんの中でも自分からぎっくり腰になったと言われる方が多いのですが、決して甘く見ていいものではありません。
今まで痛くなかったところに急に痛くなることから、海外では「魔女の一撃」と言われ恐れられています。
その名の通り、急に腰が痛くなったものはぎっくり腰に分類されるため、経験したことがある方も多い傷病です。
重症な方では、
・歩くこともままならない
・寝返りが打てない
・立ち上がれない
というような方も多く、救急者で運ばれてしまう方もいらっしゃいます。
また、あまりの痛みに仰向けで寝る際に足を伸ばして寝る事が困難になってしまう方がほとんどで、痛い方を上で横向きに寝ると楽になる事が多いです。
逆に軽症な方は
・日常生活に支障がない
・我慢できる程度の痛み
・身体をひねると違和感が出る
というような症状がでるため、ぎっくり腰を軽く考えてしまうケースも多いです。
その結果、安静にしたり治療を行わない方が多く重症になってしまう方もいるため、甘く見ないで注意することが大切です。
ぎっくり腰の原因
ぎっくり腰になってしまう原因は多くありますが、共通しているのは腰に負担がかかってしまうときに起こるということです。
重い荷物を持ち上げたときやスポーツで身体を捻ったときなど、強い負荷がかかったときがイメージしやすいと思います。
また、身体の状態によっては、床から立ち上がったときや顔を洗うためにかがんだときなど、少しの負荷でも痛めることがあります。
腰の筋肉が疲労状態だと些細な動作がぎっくり腰に繋がります。
立ちっぱなしや座りっぱなし、お酒を飲み過ぎたり、水分不足などで筋肉が固くなっている場合もぎっくり腰になりやすい状態と言えます。
更に睡眠時間が十分ではない場合は筋肉に疲労物質がたまりやすく、これもぎっくり腰の原因となります。
毎日同じ作業をしている方は疲れている意識がないまま活動している方が多いので、一度自分の普段の姿勢や水分摂取量、睡眠時間を見直すことが大切です。
他にも、腰部ヘルニアや脊柱管狭窄症、腰椎すべり症など整形外科で対応しなければならない症例や、腎臓や膵臓など腰に痛みが出てくる内臓器疾患の可能性もあるので、自己判断せずに痛めたと感じたらすぐに近くの医療機関に行くことをおすすめします。
ぎっくり腰になってしまったときの対処法と注意点
ぎっくり腰になってしまったときの対処法と注意点をお伝えします。
ぎっくり腰は簡単に言えば腰の捻挫です。
つまり、捻挫をした時の対処と同じことをすると悪化を防止できます。
スポーツをしていた方は聞いたことがあるかもしれませんがRICEという応急処置法があります。
RICEは、捻挫などや肉離れなどのケガをした際の基本となる方法です。
Rest、Icing、 Compression、Elevationの4つの頭文字から名付けられました。
まずRest(安静)は、無理に動き回ったりせず痛めた部分を悪化しないようにします。
コルセットを巻いたり横向きで寝るようにし、うつ伏せは悪化のリスクがあるので避けるようにしましょう。
Icing(冷却)は、痛めた患部を冷やすことです。
湿布では冷やす力が弱いので、氷やアイスパックをタオルで巻いて患部を冷やしましょう。
タオルに巻かないで長時間冷やすと凍傷のリスクがあるので注意が必要です。
Compression(圧迫)は、内出血を抑えて患部の回復を早くします。
テーピングや包帯で行うのですが、強すぎる力で圧迫すると逆に痛みを強くしてしまうので自身で圧迫する際は注意が必要です。
Elevation(挙上)は、痛めた部分を心臓よりも高い位置にもっていくことで腫れを抑える効果があります。
起き上がった状態では腫れがひどくなりやすいので、可能な範囲で横になることが良いと言えます。
RICE処置を行うことで痛みを抑え、けがの治りに大きな差が出るので医療機関に行くまでの間は、意識して対処しましょう。
ぎっくり腰の施術方法と治療期間の目安
当院でのぎっくり腰の治療方法と治療期間の目安をお伝えします。
ケガをしてから3日間は熱や腫れが特に強く出やすい時期なので、当院では急に痛くなりケガしたばかりの患者さんにはアイシングをしてから高周波治療を行うことが多いです。
アイシングは熱や腫れを抑える効果があるので、受傷直後は特にしっかり行う必要があります。
高周波治療器は、低周波治療より身体の奥深くまで効果が届くので、痛みの原因である患部や神経に直接届き即効性があります。
その後に身体の中でコルセットの役割をする腸腰筋や腹横筋を活性化させるために手技療法を行ったり、かばって歩いたせいで緊張が強くなっている足周りの筋肉をケアします。
そこまで治療してから残った症状に合わせて、日常生活での注意点やコルセットの巻き方などの指導を行います。
だんだんと熱や腫れがなくなってきたら、かばって悪くなった姿勢や筋肉を健康な状態に戻していきます。
傷ついた筋肉や人体が修復されて痛みがなくなるまでの期間は、順長に治療できて3週間ほどの方が多いです。
そこからケガをする前の状態になるには、仕事をしながらだと2カ月ほどかかってしまうので痛みを感じたらなるべく早く医療機関にかかることをおすすめします。
ぎっくり腰を発症しないためにはこれが大切
ぎっくり腰にならない為には普段からの生活習慣が大事になります。
毎日行うことの積み重ねがケガになりにくい身体を作っていきます。
特に意識して欲しいのは睡眠、水分補給、仕事中の姿勢、運動をこまめに行っていくことです。
まずは睡眠ですが、理想的な時間は夜の10時には寝ることをおすすめします。
夜10時〜深夜2時に睡眠をとっていると、身体の中から成長ホルモンが分泌されます。
成長ホルモンは子供の頃は身長を伸ばしてくれますが、大人になった後は筋肉の活性化に効果があり、認知症の予防にもなり様々な面で健康に良いと言われています。
次に水分補給、実は筋肉の70%は水分で構成されています。
水分は最優先で脳や内臓に運ばれるので自分では足りていると感じていても、筋肉まで水分が足りていない方が多くいらっしゃいます。
大体1時間に吸収できる量が200mlほどなので、こまめに水分補給し1日2L取ることを意識して生活することが大切です。
仕事中の姿勢は、背筋を伸ばして骨盤の真上に頭が来るようにするのが大切です。
丸まった姿勢だと肺が圧迫されて、酸素がしっかり肺に行き届きにくくなります。
酸素が筋肉中の疲労物質を回収してくれるので、酸素不足だと疲労物質だらけの疲れた傷つきやすい筋肉になってしまいます。
最後に運動ですが、急にランニングなどの高負荷の運動をするとケガに繋がる可能性が高いです。
1週間に2回ほど8千歩を目標に歩くことや毎日ラジオ体操を行う習慣にして、物足りなくなったら徐々に負荷を上げていき
健康的な身体を作り上げていくことが大切です。
ぎっくり腰Q&A
Q.ぎっくり腰は何日くらいで治りますか?
A.ぎっくり腰は、腰の関節周りの筋肉や靭帯が傷つき発症する捻挫です。
筋肉や靭帯が修復されてカサブタ状態になるまでは、3週間ほどかかります。
ここまでくると痛みはほぼなくなりますが、強めの負荷がかかると再発しやすい状態になります。
カサブタから元の状態になるのに2か月~3か月ほどかかり、ここまでくれば再発することはほぼ無く、再び痛くなった場合は違う原因が考えられます。
Q.ぎっくり腰とヘルニアの違いは何ですか?
A.ぎっくり腰は、捻挫であり筋肉や靭帯の損傷です。
それに対して、ヘルニアは椎間板という背骨の間にある軟骨が潰れたことによって、近くの神経が圧迫されしびれや痛みを起こすものです。
筋肉や靭帯と違い軟骨は、再生させることが難しいため周りの筋肉でフォローするか手術が必要になるケースがあります。
ぎっくり腰かヘルニアの鑑別にはMRIが効果的なので、もしも不安な方は近くのMRIのある医療機関を受診することをおすすめします。
Q.ぎっくり腰になった場合、温めるのと冷やすのはどちらがよいですか?
A. 症状や受傷後にどのような生活を送るかによって変わって来ますが、受傷から3日は冷やしてその後は温めるケースが多いです。
患部の熱の有無で判断するので、不安な方はお近くの医療機関を受診することをおすすめします。
Q.ぎっくり腰は安静にしていればどれくらいで動けるようになりますか?
A.症状にもよりますが軽傷なら3日、重傷な場合2週間ほどかかる事もあります。
そして動けるようになっても治っているわけではないので、再発のリスクが高くケガの前まで戻る為には数ヶ月かかることが多いです。
しっかり治そうと接骨院に行く場合は受傷してからすぐの治療をおすすめします。
自然治癒力はケガをして3日が1番強く、このタイミングで治療できると治りが良くなり、3週間以上治療までに期間を開けてしまうと自然治癒力はとても下がるので完治まで時間がかかるケースが多いです。
Q.ぎっくり腰になった場合、何日目からお風呂につかっても大丈夫ですか?
A.患部の熱が引いてからでないと入浴後痛みが強くなる事があります。
3日が目安ですが、個人差があるので医療機関で見てもらうか痛みがなくなってから入浴することが良いと言えます。
Q.ぎっくり腰を繰り返さないためにはどうすればよいですか?
A.ケガをした筋肉が正常な筋肉になり姿勢を正しい位置にすることが大切です。
そして、身体の土台であるインナーマッスルと下半身を鍛えることで再発のリスクを抑えることができるので、自己判断で治療を中止せずに主治医の先生と話し合いながら治療を受けていただきたいです。
Q.運動不足ですとぎっくり腰になりやすいのでしょうか?
A.運動不足の場合、筋肉に柔軟性がなく疲労物質が溜まっている状態なので少しの負担でも痛めやすくなっています。
睡眠、水分補給、ストレッチなど習慣にして健康な身体を目指していくことが大切です。
Q.ぎっくり腰になったときはアルコールはいつまで控えた方がよいのでしょうか?
A.アルコールは、患部の痛みや腫れを強くしてしまう作用があるので受傷直後の飲酒は厳禁です。
患部にカサブタができるまでの3週間は飲酒を控えると、ケガの治りが良くなるのでお酒好きな方は大変ですがなるべくその期間はお酒は飲まない方が良いと言えます。